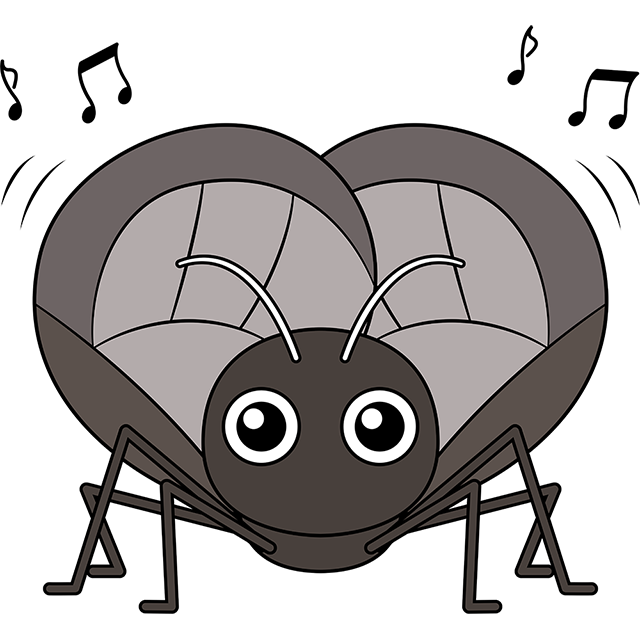
秋と言えば、鳴く虫の季節ですよね。皆さんは鳴く虫と言えば何を思い浮かべますか?鳴く虫もたくさんいますよね。
たくさんいるだけあって、様々な鳴き声を聞く事ができます。残暑が残る時期に、虫の鳴き声は聞くだけでも清涼感を覚えるのではないでしょうか。
具体的に日本で見られる秋の鳴く虫はどんな虫がいるのでしょうか。
例えば、鈴虫、コオロギ、松虫、キリギリス、カタタタキ、カンタン、クツワムシ、ウマオイ、クサヒバリ、ササキリ・・・などなど。数えればキリがありませんし、コオロギにも色んな種類がいますし、本当にたくさんの鳴く虫がいます。
今回はそんな鳴く虫の中から、「鈴虫(スズムシ)」の鳴き声について調べてみました。
また鈴虫の飼い方については、以下の記事にて詳しく紹介していますのでぜひご覧ください。
目次
鈴虫が鳴く理由とは?
鈴虫は実にきれいな声で鳴きます。「リーン、リーン」という鳴き声が特に有名ですよね。
では一体どうして鈴虫は一生懸命にきれいな鳴き声を出すのでしょうか。
その理由は「求愛のため」なのです。鈴虫は鳴くのはオスの成虫だけで、子孫を残すためにパートナーとなるメスを呼ぶための鳴き声だったんですね。
鈴虫の鳴き声
鈴虫の鳴き声のパターン「誘い鳴き」と「本鳴き」
鈴虫の鳴き声は「リーン、リーン」が一般的ですが、実はそれだけではないのです。リーン、リーンという鳴き声は鈴虫にとっては力強く鳴いている鳴き声で、先ほども述べたようにメスを呼ぶための鳴き声です。この鳴き声を出す鳴き方を「誘い鳴き」と呼びます。
ですからオスがいる場所にメスを一緒に入れると、この誘い鳴きをするようになるのです。
美しい鳴き声ですが、当の鈴虫にとっては短い命の間にメスを獲得するために、必死で鳴いていたのですね。
もう一つの鳴き声は、前述の「誘い鳴き」とは違った鳴き声で、「リー・・リー・・」といった具合に何とも力の抜けたように聞こえる鳴き声を出すことがあります。
この鳴き声を出すときはメスが一緒にいないとき、オスが一匹でいるときなどに聞く事ができます。
この鳴き声は「本鳴き」と呼ぶようです。本鳴きと言いますが、実際に聞くのはやっぱり「リーン、リーン」の誘い鳴きの方が多いですよね。
一度聞いてみたい方は、試しにオスを一匹隔離してみましょう。本鳴きが聞けると思いますよ。
鈴虫が美しい鳴き声が出せるメカニズムとは?
皆さんはどうして鈴虫があれだけ美し鳴き声が出せるのか、疑問に思ったことはありますでしょうか。
鈴虫だけでなく、秋に鳴く虫はすべて同じ原理でそれぞれ独自の美しい鳴き声を出しているんです。
そのメカニズムとは、「前翅(まえばね)をヤスリのようにこすり合わせて音を出していた」のです。
なんと驚いたことに、鈴虫が一回「リーン♪」と鳴くために、40回も前翅をこすり合わせていたという事実です。すごい速さですよね。
鈴虫の後翅は抜け落ちるもの
前翅があるように、鈴虫には後翅(うしろばね)も持っています。しかし鈴虫は鳴くために前翅を使うものの、後翅は使うことがありません。
ですので鈴虫が羽化した後、しばらくして後翅は抜け落ちるという特徴もあるのです。
もちろん完全に抜け落ちずに片方だけ残っている鈴虫もいたりします。ですから後翅がない、または片方しか残っていないからと言って奇形であるわけではないのですね。
鈴虫の鳴き声は電話越しには聞こえない!?
面白い話があります。それは、「鈴虫の鳴き声は電話越しには聞こえない」というものがあります。
これは果たして本当なのでしょうか。答えは「本当」のようです。このカラクリは音の周波数に秘密があります。
どうやら電話機(携帯、スマホ)の周波数は300〜3400Hzなのに対して、鈴虫の鳴き声の周波数は4500Hzだと言います。
聞こえないのにはこういう理由があったんですね。鈴虫の鳴き声の他にも、探せば聞こえない音がありそうですよね。
鈴虫の鳴き声には癒しの効果がある!?
昔から鈴虫は虫かごに入れられ、売られてきたという古い歴史があります。
江戸時代にも「虫売り」という商人がいて、実際に鈴虫を販売していたと言います。
購入する人たちも鈴虫の美しい鳴き声に癒しを感じていたのでしょうか。実は鈴虫の鳴き声には本当に癒しの効果があると言われているのです。
具体的には「鈴虫の鳴き声にはストレスを減少させる効果がある」と認められているようです。
人間は川のせせらぎや鳥の鳴き声といった自然の音に心癒され、疲れが取れると言いますが、実は鈴虫の鳴き声もこうした自然の音ですので、同じようにストレス減少に効果があるというわけです。
鈴虫が鳴かない、鳴きにくい時は?
鈴虫を飼っているけれど、鳴いてくれないという声を聞く事が稀にあります。
これにはいくつか原因がありますので、一つずつ確認していきましょう。
オスがいない
鈴虫が鳴くのはオスだけです。メスは一切鳴き声を出しません。飼っている鈴虫がメスばかりでないか、もう一度確認してみましょう。
羽化していない
鳴くのは成虫になった(羽化した)オスだけです。オスがいたとしても、羽化していない幼虫のオスは鳴き声を出しません。
飼育している環境に問題がある
鈴虫は夜行性です。ですので明るい場所では鳴きにくいという特徴があります。鈴虫を入れているケージを暗がりに置いてみるなど、飼育環境をもう一度見直しましょう。
メスがいないか、オスが少ない
そもそも鈴虫が鳴くのはメスをの気を惹くための求愛行動ですので、メスがいないと鳴きづらいと言えます。
またオスは他のオスが鳴いているとつられて「連れ鳴き」をすることが多々あります。あまり鳴かないという場合はオスをもう少し増やしてみましょう。
画像で見るオスとメスの違い
成虫のオスとメス
オスは翅が丸い大きな形をしているのが特徴で、メスはおしりに一本の長い管(卵管)があるのが特徴です。
幼虫のオスとメス
幼虫のころからメスのおしりには卵管が確認できます。
まとめ
いかがでしょうか。鈴虫の鳴き声一つを見てみても、本当に奥が深くて面白いですね。
鈴虫は普通に飼育していると鳴き声を出してくれますが、場合によっては鳴いてくれない、あまり鳴きにくい事もあるようです。
そういった場合には飼育環境を見直して見てください。鈴虫が鳴きやすい環境をまとめてみましょう。
1.温度が25℃以上あること
2.成虫のオスとメスを複数匹同じケージに入れて飼う
3.鈴虫のケージを薄暗いところに置く
この3つの条件を満たしていれば、自然と美しい声でたくさん鳴いてくれると思います。
メスのために命を燃やすように一生懸命に鳴いているオスの姿を見ていると、自分も頑張ろう!という気持ちになってくると思いませんか?
残暑厳しい季節に清涼感を与えてくれる鈴虫。一度飼育してみてはいかがでしょうか。

